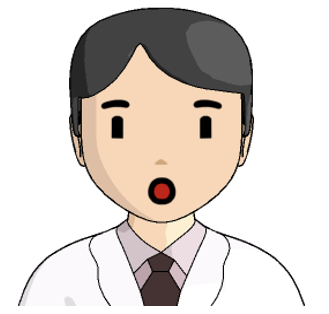
もう少し人を増やしてほしい
薬局で働いていると、こういう希望って自然と出てきますよね。
でも、ただ『必要です!』と率直に伝えたとしても、なかなか話が進まないことってありませんか?
それって、結局のところ、『こうして欲しい!』という願望だけを伝えてしまっている状態なんですね。
上司や経営者が意地悪で聞いてくれないわけじゃなくて、現場と経営では見ているポイントが違うからなんです。
以前の記事(『薬局の数字』の2回シリーズ)でも触れましたが、
- 管理薬剤師の視点:現場の業務をスムーズに、効率よく回したい
- 経営者の視点:利益を出し続け、薬局を安定運営・成長させたい
どちらが正しい・間違っているという話ではなく、見ているポイントが違うんです。
だからこそ、申請書を書くときも『経営者の視点で伝える』ことが大事なんです。
そうすれば、結果的に現場の要望が通りやすくなります。
今回は、申請書や業務連絡書をどう書けば効果的かを、経営者の視点も交えて解説していきます。
目次
申請書の書き方
申請書って簡単に言うと、『会社に正式にOKをもらうための書類』です。
とはいえ、『何を書けばいいの?』とか『どんな風に伝えれば通りやすいの?』って悩むこともありますよね。
そこで、実際の現場でよくあるケースをもとに、申請書の書き方を具体的に解説していきます。
たとえば、こんなケースがあります。
現場でよくある申請の例
実際に申請が必要になる場面を、3つほど紹介します。
①調剤機器の導入申請
例えば、監査システムを新しく導入したい場合、どう説明すればいいかを考えてみましょう。
・この監査システムを導入すれば、監査にかかる時間が短縮されます。
・その結果、1人あたりの待ち時間が平均30秒短縮され、患者さんの満足度がアップします。
・特に、高齢者の方や忙しいビジネスパーソンにとって、短い待ち時間は大きなメリットになります。これが続くと、再来局率の向上にもつながる可能性があります。
このように、数字を使って説明することで、より説得力が増します。
単に『便利だから導入したい』と言うだけではなく、『これだけの改善が期待できる』を示すことで、経営者や上司にも納得してもらいやすくなります。
②研修会・勉強会の参加費申請
薬剤師としてのスキルアップや研修義務を満たすためにかかる費用を申請する際、どう説明すれば効果的かを考えてみましょう。
・この研修を受けることで、かかりつけ薬剤師指導料(76点/回)の要件を満たせます。
・もし月に20名の患者さんに指導した場合、月額15,200円、年間で182,000円の増収が見込めます。
具体的な数字を示すと、経営者にも『それなら納得できる』と思ってもらいやすくなります。
こんな感じで、研修の効果を数字で具体的に伝えることがポイントです。
これなら、単なる『スキルアップのため』と言うよりも、実際にどれだけの利益が生まれるかがしっかり伝わります。
③人員増員の申請
忙しくて薬剤師が足りない時ってありますよね。
そんな時、どう説明すれば増員を認めてもらいやすいか考えてみましょう。
・今、ピーク時の待ち時間が30分を超えていて、患者さんの満足度が下がっているのが心配です。
・さらに、薬剤師1人あたりの負担が増えて、残業が月に10時間発生している状況です。
・もし薬剤師を1名増員できれば、待ち時間を平均5分短縮できるだけでなく、患者さんの再来局率がアップし、年間で144万円の売上増が見込めます。
・さらに、業務負担が軽減されれば、残業時間を50%削減でき、年間で60時間削減できるため、コスト面でも効果が出ます。
こうやって、数字を使って具体的に説明すると、『確かに必要だな』と経営者も納得してくれるかもしれません。
単に『人手が足りない』と言うだけでなく、具体的な改善点や見込める効果をしっかり伝えることが大事です。
申請書を通すコツは『相手の視点』を意識すること
申請書を書いていると、どうしても『うまく書けないな』と感じることありますよね。
でも、大丈夫です。
実は、申請書作成にはちょっとしたコツがあって、それさえ押さえておけば、誰でも経営者を納得させる内容が書けるようになります。
一番大切なのは、『相手の視点』を意識することです。
経営者は、現場の状況や忙しさも理解していますが、それ以上に大事なのは経営面でのメリットです。
だから、申請書には『なぜこれが必要か?』と『どんなメリットがあるのか?』をシンプルに、そしてわかりやすく伝えることがポイントです。
そして、できればそのメリットを数字で裏付けると、説得力がぐっと増します。
具体的に注意すべきポイントは、以下の3つです。
現場の状況を具体的に伝える
『忙しい』と言っても、経営者には具体的なイメージが湧きません。
例えば、『今、処方箋の数が1日平均〇〇件増えています』と具体的に書くと、状況が伝わりやすいです。
数字を使って説得力を出す
『効率アップ』って言うだけでは、何がどれだけ改善されるのかが分かりません。
例えば、『1件あたりの待ち時間を〇分短縮できます』と具体的な数字を示すと、より効果的です。
会社にとってのメリットを明確にする
『楽になる』というだけでは、経営者には響きません。
例えば、『新しいシステムを導入することで、年間〇〇万円のコスト削減が見込めます』と、会社にとってどういう経済的なメリットがあるかを示すことが大事です。
これら3つの視点を意識すれば、経営者が納得しやすい申請書が書けるようになりますよ。
申請書を書くときに気をつけたい3つのポイント
実際に申請書を作成するとき、どのように書けばうまく伝わるか、3つのポイントを紹介しますね。
タイトルは一目で内容が分かるように
例えば、『設備投資について』とだけ書くのではなく、『〇〇導入で業務効率を改善する申請』のように、読んだ瞬間に内容が分かるタイトルにしましょう。
これだけで、相手の読む気を引きます。
経営層に響く書き方を心がける
経営層は現場の細かい事情にまで目を通す時間はありません。
だから、必要な情報だけをシンプルに、そしてわかりやすく伝えることが大事です。
- 費用対効果を示す
例えば『効率化します』だけじゃなくて、『年間△時間削減=人件費〇万円削減』と具体的に書くと、経営層も納得しやすい。 - 簡潔に書く
長々と説明せず、箇条書きなどで簡潔にまとめる。 - 会社にとってのメリットを明確に
『この申請が通ることで、会社にどんな利益があるのか』をハッキリと数字で書くと、経営層も納得しやすい。
投資か浪費かを意識する
経営層が気にするのは、『本当に必要なのか?』と『コストに見合うリターンがあるのか?』という視点です。
新しい機器を導入したいです
この機器を導入すれば、1日〇分の業務短縮が可能で、年間〇万円のコスト削減が見込めます
このように、具体的な数字を示すと、より説得力が増します。
申請書はただの『お願い』ではなく、『経営者を納得させるための文書』です。
感情的に『これが必要です!』と伝えるのではなく、『これをすれば、会社にこんなメリットがあります』とロジカルに伝える方が、申請が通りやすくなります。
管理薬剤師として、現場の声だけでなく、経営者の視点を意識した申請書を作成できると、よりスムーズに業務を進められるようになります。
業務連絡書の書き方
業務連絡書って、簡単に言うと『職場で大事なことをきちんと伝えるための書類』です。
管理薬剤師として、こんな場面、経験したことがありませんか?
- スタッフから『○○の報告、どう書けばいいんですか?』と聞かれる
- ミスが起きたけど、情報共有がうまくいかず、同じミスが繰り返される
- 本部やオーナーに何か伝えたけど、『聞いてない』と言われる
こういった問題を避けるためには、業務連絡書が役立ちます。

口頭で伝えてもいいんじゃない?
と思うかもしれませんが、実はそれだと後々問題が起きることが多いんです。
例えば、こんな問題が起こりがちです。
- 伝えたつもりでも、相手がちゃんと聞いていなかった
- 時間が経つと内容があいまいになって、『そんな話しましたっけ?』と言われる
- 言った内容にズレが出て、後でトラブルに発展する
こういった経験、誰でも一度はあるのではないでしょうか?
業務連絡書を使えば、『言った・言わない』のトラブルを防げるだけでなく、正確に情報を伝えることができます。
業務連絡書が必要な場面
薬局で業務連絡書を使うのは、こんな場面です。
例えば、よくあるシーンを挙げてみますね。
- ミスが起きたときの報告
例:調剤ミス、請求ミス、返金ミスなど - 重要な連絡事項
例:シフト変更、店舗ルールの変更、接遇マナーの再確認など - 本部やオーナーへの報告
例:クレーム対応、調剤過誤対応、業務改善提案など
業務連絡書は単なる報告書ではなく、『相手にしっかり伝えるためのツール』です。
このあと、実際の事例を交えて、どう書けば良いか(NG例とOK例)を具体的に解説していきます。
業務連絡書のNG例とOK例
では、ちょっと具体的に業務連絡書のNG例とOK例を見てみましょう。
例えば、『医療事務研修の欠席届を出し忘れた』というケースを考えてみます。
NG例とOK例を比較してみると、その違いがはっきり分かります。
□月〇日の医療事務研修を無断欠席しまして誠に申し訳ございませんでした。
決して避けている訳ではなく家内の病気、又私自身の病気等偶然にも重なり、結果的に長期間に渡り医療事務研修を欠席してしまっているのが現実です。
私自身も決して平気で過ごしている訳では無く、気にかかっているのは正直な気持ちです。
今回の事につきましては、私の祖母が急に亡くなり、その知らせを受けて気が動転してしまい、ついうっかり連絡を忘れて、実家の方に駆けつけたと言うのがいきさつです。
今後は研修に対しては、必ず出席する事をここに約束いたします。
また、いかなる小さな理由であろうと予定が変更になる場合は、事前に連絡を入れる事もここに約束致します。
私の不注意によって多大なご迷惑をおかけした事を、深くお詫びすると共に今後この様な事が無い様に深く注意いたします。
本当に申し訳ございませんでした。
こんなパターン、現場ではよくありますよね。
謝っているし、理由も書いてある。
でも、上司がこれを見たとき、なんとなくスッキリしない気持ちになることが多いんですね。
上司としては、まるで自分がスタッフを『責めている』とか『いじめている』感じになっちゃうかもしれません。
でも実際、上司や経営者が一番気にしているのは、謝罪や理由よりも『これからどうするか』なんですよね。
もちろん謝ることは大事ですけど、それ以上に大事なのは、『同じミスを繰り返さないためにどう対策するか』をしっかり伝えることです。
それが曖昧だと、なんとなく不安が残ってしまいますよね。
では、OKな例を見てみましょう。
□月〇日の医療事務研修を無断欠席いたしました。
1.理由
私事で恐縮ですが、祖母が急逝し、急遽実家に帰らなければならなくなり、その際、研修欠席の連絡を失念してしまいました。
大変申し訳ございません。
2.対策
【応急処置的対応】
・今回欠席した研修に関しては、遅れた部分を別の研修で補う手続きを取る予定です。
・今後欠席が発生した場合、必ず事前に連絡をし、代替の研修日程を早急に調整します。
・研修担当者には、欠席分の内容について個別に確認し、理解度をしっかり確認した上でフォローアップします。
【今後の対策】
・研修スケジュールを自分のカレンダーに加え、研修前日にリマインド通知が届くように設定します。
・急用が入った場合でも、できる限り前日までに代替日を調整し、欠席のリスクを減らします。
・スケジュールに余裕を持たせ、急な事情に対する対処法(例えば、家族の急な病気など)を予め共有しておき、周囲の理解を得られるようにします。
二度とこのようなことがないよう、最善を尽くします。
申し訳ございませんでした。
以上
どうでしょうか?
このように理由と対策(応急処置と今後の対策)をしっかり伝えることが大切です。
これなら、相手も『なるほど』と思って安心できる内容になると思います。
問題があった場合、その後どう対処するかがはっきりしていると、相手にも信頼感を与えられます。
では、最後に業務連絡書を書く際のポイントを具体的に紹介していきますね。
業務連絡書の書き方(3つのポイント)
業務連絡書を書くとき、ちょっとした意識の違いで伝わり方が大きく変わります。
以下の3つのポイントを意識してみてください。
- 『何があったか』だけでなく『これからどうするか』を伝える
- 簡潔に書き、余計なことは省く
- 『誰に向けたものか』を意識して、伝えたい内容を整理する
この3つの意識を持つだけで、業務連絡書は『書かされるもの』ではなく、『自分たちの仕事をスムーズにするツール』に変わります。
業務連絡書を書く際には、ただ自分の気持ちや伝えたいことを述べるだけではなく、『相手にどう伝わるか』をしっかり考えることが大切です。
上司や経営者が一番気にしているのは、ミスそのものよりも『これからどうするのか?』という点です。
だから、業務連絡書は単なる謝罪の場ではなく、『安心につながる報告』にしましょう。
業務連絡書を書くときに意識したいのは、『ミスの理由を書く』だけで終わらず、『今後どうするか』をしっかり書くことです。
この2つを意識するだけで、相手にとって納得感のある業務連絡書になります。
『読んだ人がどう感じるか?』を考えながら、伝わりやすい業務連絡書を作成していきましょう。
まとめ
今回は、管理薬剤師向けに申請書と業務連絡書の書き方についてお話ししました。
申請書を通すコツは、経営者の視点を意識すること。
経営者が何を重視しているのかを考え、現場の状況やその提案がどれだけのメリットをもたらすのかを具体的に数字で示すと説得力が増します。
数字で示すと、相手も『なるほど』と納得しやすくなります。
一方、業務連絡書は、口頭だけではなく書面でしっかり伝えることが大事です。
口頭で伝えると忘れがちになったり、誤解を招いたりすることもありますよね。
書面を使えば、後で振り返ることができ、情報が漏れにくくなります。
これらのポイントを意識して書類を作成すると、現場のニーズもしっかり伝わり、管理薬剤師として職場環境の改善にも繋がります。
経営の視点を持ちながら実践すれば、より頼りにされる管理薬剤師になれるはずです。
そうすることで、現場スタッフからも経営者からも信頼される唯一無二の存在になれると思います。
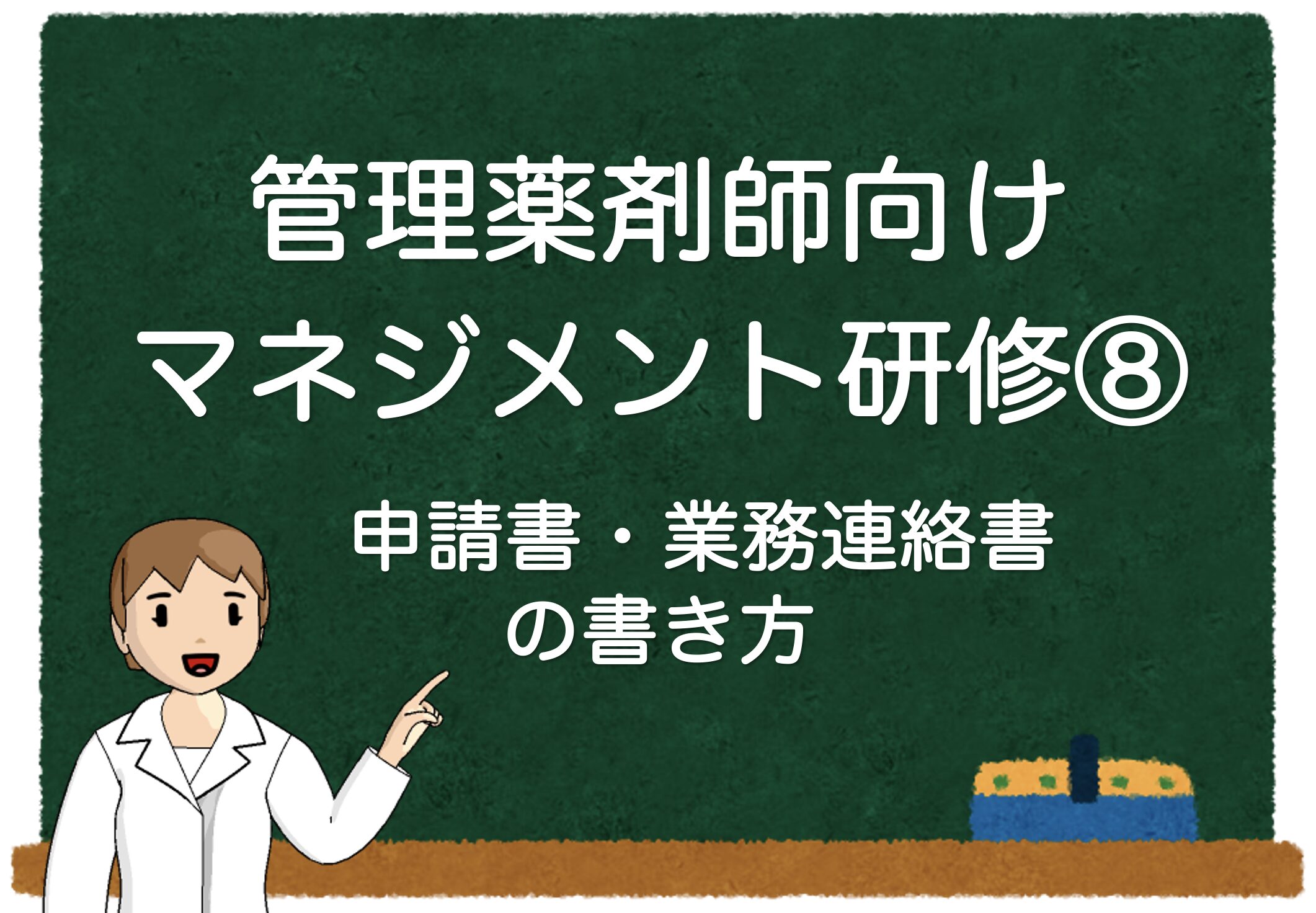
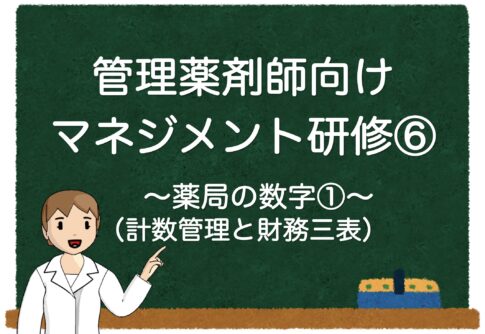
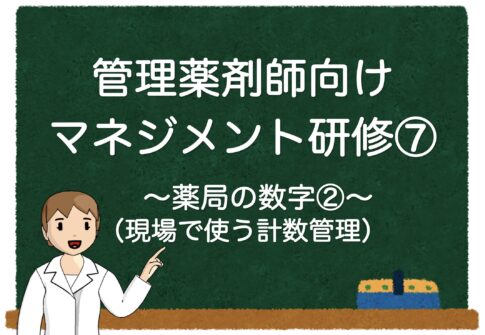
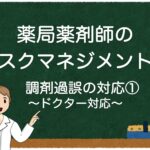
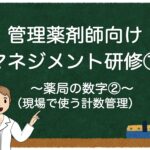
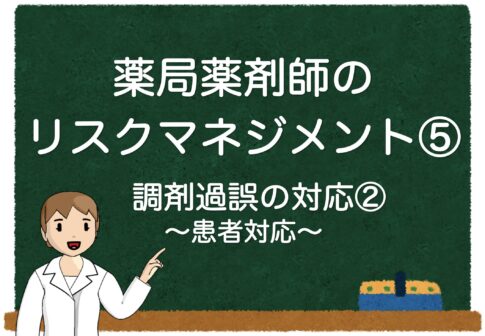
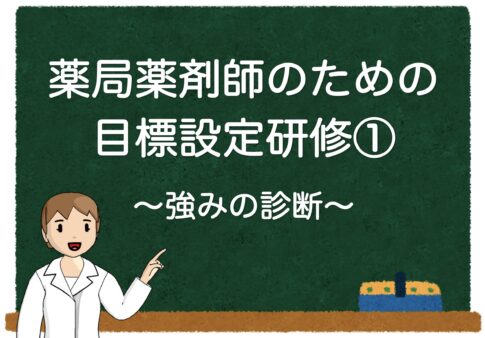
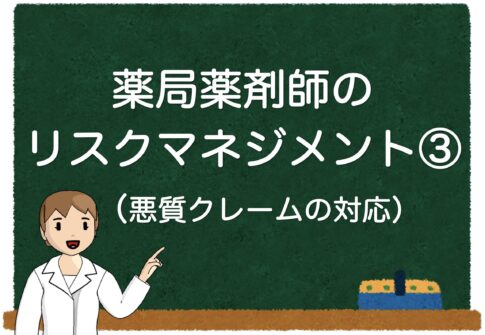
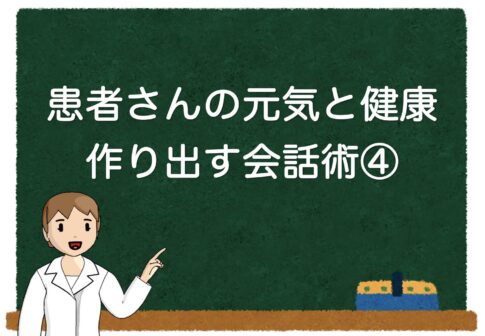
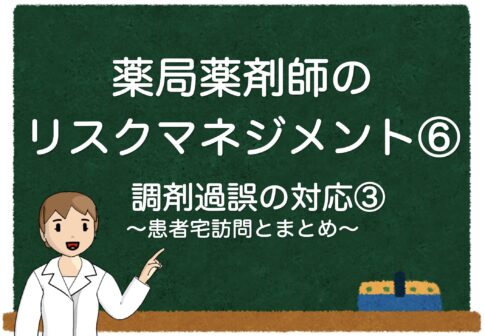
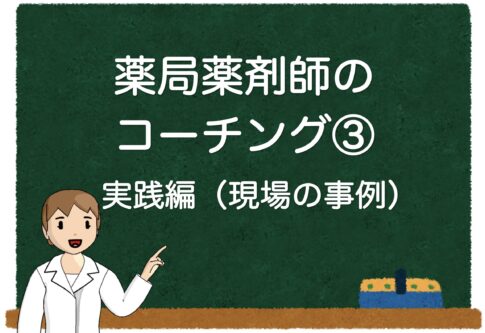
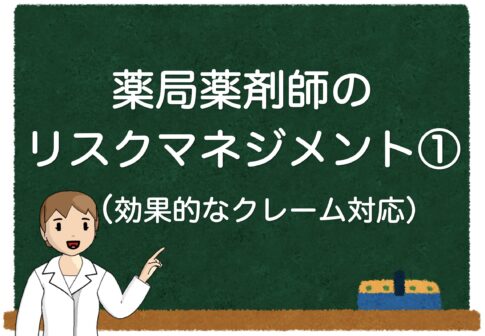
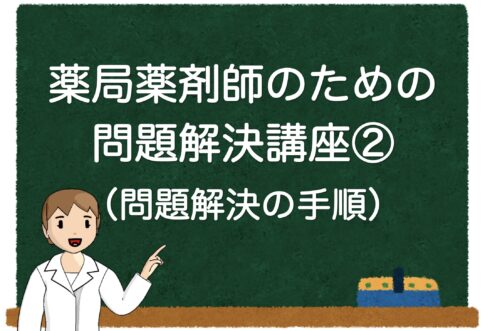

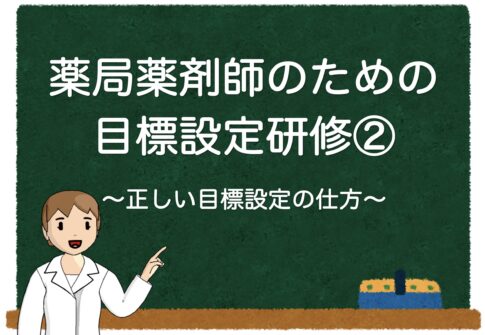

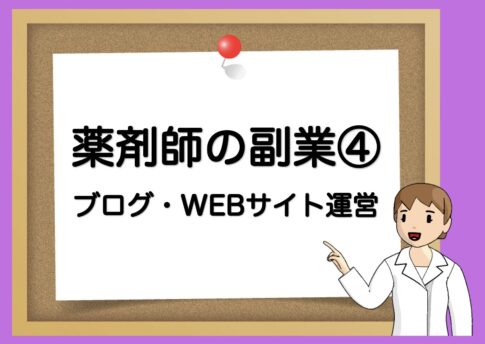
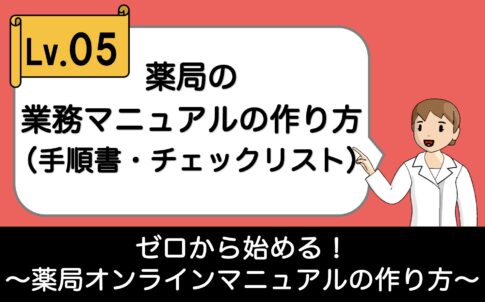
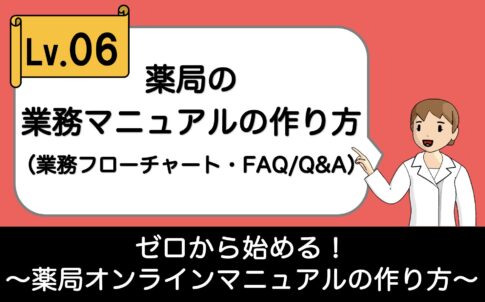

この調剤機器を導入したい