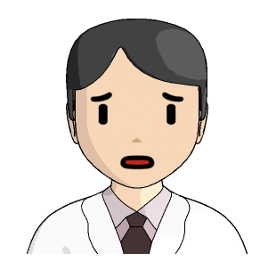
患者さんに何をどう伝えればいいのか…?
怒られたらどうしよう…
こんな不安を感じたこと、ありませんか?
調剤過誤が起こったとき、患者さん(またはご家族)への電話連絡って、正直プレッシャーがかかりますよね。
でも、伝え方ひとつで患者さんの不安を和らげたり、信頼を取り戻せることもあります。
逆に、対応を間違えると、余計な不信感を招くことも…。
前回は、調剤過誤が起こったときの【STEP1】『ドクターへの報告と確認』について解説しました。
具体的な会話例を交えながら、報告や確認の仕方を説明しました。
ここをしっかり押さえておくと医師との連携がスムーズになり、患者さんへの対応の質も変わってきます。
前回も紹介しましたが、調剤過誤時の対応は下記の通り。
- 【STEP1】ドクターへの報告と確認(前回解説)
- 【STEP2】患者さん(またはご家族)への電話連絡(今回解説)
- 【STEP3】患者宅訪問と謝罪(次回解説)
そこで今回は、【STEP2】『患者さん(またはご家族)への電話連絡』 について、 実際の現場で使える伝え方やポイント を分かりやすく解説していきます。
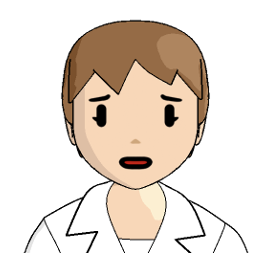
いざというとき、どう話せばいいのか分からない…
そんな不安を感じている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
患者家族への電話連絡
実際の電話の会話例を紹介する前に、電話連絡のときに気をつけたい5つのポイントを整理しました。
電話をする際に慌てないよう、事前に押さえておきましょう。
いきなり本題に入らない
電話をかける側としては、すぐに『お薬のことで…』と話したくなりますが、それだと相手は身構えてしまいます。
まずは患者さんの様子を尋ね、家族の気持ちを受け止めることが大切です。

お母様のご様子はいかがでしょうか?
- 『この人は母のことを本気で心配してくれている』と感じてもらうことが大事
- 急いで本題に入りたくなっても、一呼吸おいて様子を確認する
先に共感の言葉を伝える
調剤過誤の話をすると、相手は驚いたり、不安を感じたりします。
いきなり謝罪するよりも、
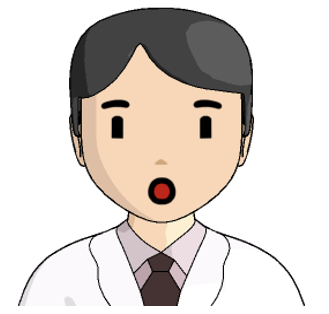
ご心配ですよね。
突然のご入院で大変なお気持ちかと思います。
など、共感の言葉を先に伝えることで、相手の気持ちが少し落ち着きます。
- 『この人は分かってくれている』と思ってもらえるように共感の言葉を入れる
- 冷静に伝えようとしすぎて、機械的に聞こえないようにする
事実だけを落ち着いて伝える
焦って説明すると、かえって誤解を招いたり、相手の不安を煽ることになります。
『確認した事実』を明確に伝え、不確かなことは言わないようにしましょう。

本来の量と異なっていました
- 『◯◯のはずでしたが、◯◯になっていました』とシンプルに伝える
- 『ミスしました』と言わず、冷静な表現を使う
医師の意見は客観的に伝える
『薬の影響で入院したんですか?』と聞かれたとき、すぐに『違います!』と否定してしまうと、不信感を持たれることもあります。
医師の見解をもとに、冷静に説明しましょう。
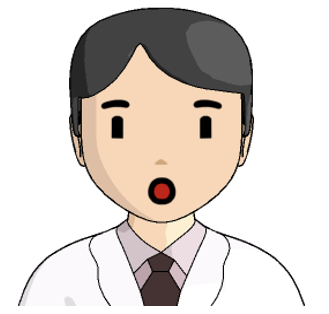
主治医の先生の意見では、心不全の進行が主な原因と考えられますが、お薬の量が影響した可能性も否定はできないとのことです。
- 『全く影響はなかった』と断言しない
- 主治医の意見として伝え、客観的な事実を整理する
まずは謝罪を明確に伝える
『でも、影響はなかったようですし…』などと弁解から入ると、『責任逃れをしている』と受け取られがちです。
まずは

申し訳ございません。
としっかり謝罪し、そのうえで再発防止策を伝えることが大切です。
- 謝罪の言葉を最初にしっかり伝える
- 『今回のことを重く受け止めています』と自分たちの気持ちも伝える
- 再発防止策は『チェック体制を強化します』と具体的に伝える
患者さん(またはご家族)への電話連絡は、伝え方ひとつで印象が大きく変わります。
『とにかく謝る』『とにかく説明する』ではなく、相手の気持ちに配慮しながら、落ち着いて事実を伝えることが大切です。
このあとは、具体的な電話の会話例を紹介します。
患者さんorご家族との会話例
先ほどの5つのポイントをふまえて、実際に電話でどのように話せばいいのかを見ていきましょう。
一般的には、次の5つのステップで進めるとスムーズに伝わります。
【Step1】電話の開始
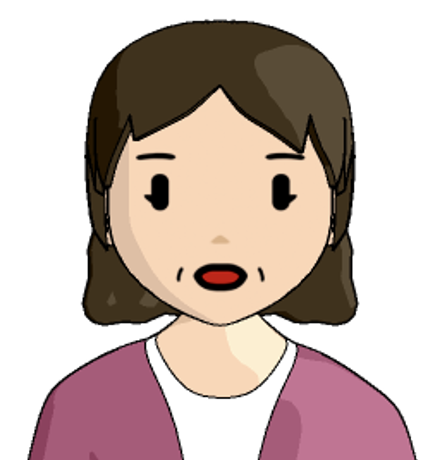
はい、○○です。

○○さん、突然のお電話失礼いたします。
私、□□薬局の△△と申します。
今、お時間よろしいでしょうか?
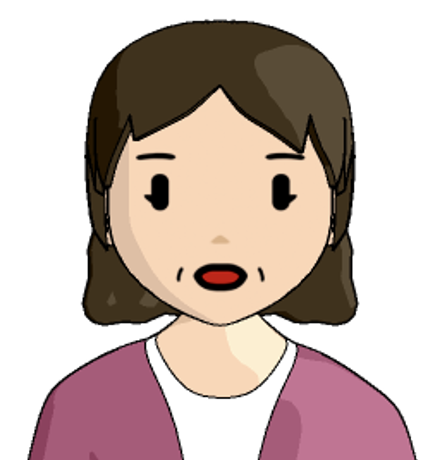
はい、大丈夫ですが…何かありましたか?

ありがとうございます。
実は、お母様のお薬について大切なお話がございます。
お電話でのご連絡となり恐縮ですが、まずはお母様のご様子はいかがでしょうか?
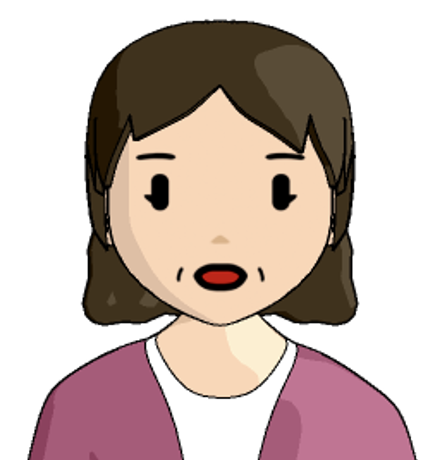
今、入院中で……とても心配しています。

そうですよね。
突然のご入院で、ご家族の皆様も大変ご心配のことと思います。※
※ ここで共感の言葉を入れ、相手の気持ちを受け止める。
【Step2】事実の説明

今回、お母様にお渡ししたお薬について確認したところ、本来お渡しすべきフロセミド40mg2錠のところ、1錠のみのお渡しとなっていたことが分かりました。
お薬の量が本来の処方と異なっており、ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
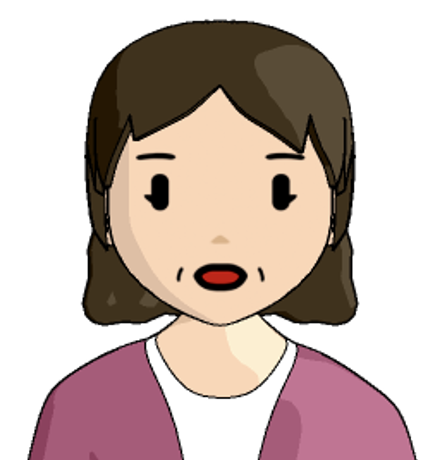
じゃあ……母が入院したのは、そのせいなんですか?

ご家族として、そう思われるお気持ちは当然かと思います。
私も気になり、すぐに主治医の先生に確認いたしました。
先生のお話では、『心不全の進行が主因と考えられるが、フロセミドの減量も要因の一つになった可能性もある』とのことでした。※
※ ここで医師の見解を客観的に伝える。
【Step3】ご家族の気持ちを受け止める
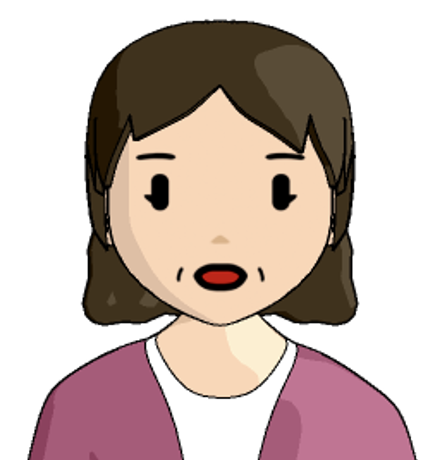
でも、こんなことが起きたら困りますよね……

おっしゃるとおりです。
このたびは、調剤に不備があり、ご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
私たちも今回の件を大変重く受け止め、深く心を痛めております。
薬局のスタッフ一同、今回の出来事を真摯に反省し、二度と同じことが起こらぬよう確認体制を一層強化してまいります。
【Step4】再発防止への取り組みを伝える

今後は、お母様にお薬をお渡しする際、ダブルチェックを徹底し、ご家族の皆様にも安心していただけるよう努めてまいります。
【Step5】最後の謝罪と締めくくり

このたびは、私どもの不手際により、ご迷惑とご心配をおかけし、本当に申し訳ございませんでした。
お母様の一日も早いご回復を、心よりお祈り申し上げます。
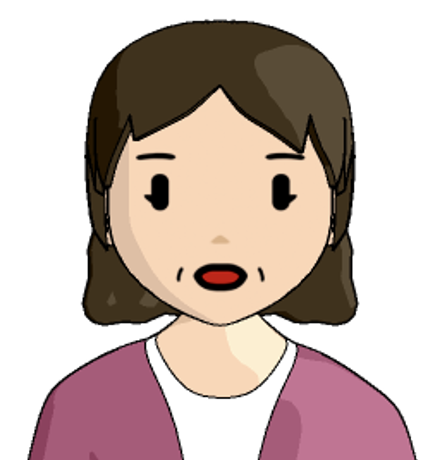
わかりました……。
(通話終了)
電話の際の8つの注意点
先ほどの会話例をもとに、実際の電話対応で特に注意したい8つのポイントを具体的に紹介します。
このポイントを意識して対応することで、相手に安心感を与え、スムーズに問題解決に向かうことができます。
それでは、どのように実践するかを見ていきましょう。
感情的にならず、冷静かつ誠実に対応する
相手が感情的になっても、こちらが慌てて反応してしまうと、逆に不信感を持たれてしまうことがあります。
落ち着いて、穏やかな声で対応することが大切です。
まずは相手の気持ちに寄り添い、

ご心配ですよね
といった共感の言葉を伝えると、相手も安心し、スムーズに話が進めやすくなります。
『ミス』『誤って』などの直接的な表現を避ける
『誤りがありました』と言うと、相手がもっと怒ってしまうことがあります。
なので、

お渡ししたお薬の量が異なっていました
など、冷静に事実を伝える表現を使うと良いです。
『不足していました』や『処方内容と違っていました』など、状況に合った言葉を選んで、きちんと事実を伝えることが大切です。
患者家族の怒りを想定しておく
もし『お母さんが入院したのはそのせいなのか!』と強く責められた場合、感情的に反論するのは避けましょう。
大切なのは、相手の気持ちを理解し、共感を示すことです。
例えば、

そのようにご心配されるのは当然のことだと思います。
だからこそ、私たちも医師と連携して、今後の影響について慎重に確認しています。
といった言葉を伝えると、相手の不安を少しでも和らげやすくなります。
冷静に、相手の気持ちに寄り添いながら話を進めていくことが重要です。
医師の見解は客観的に伝える
例えば、

医師によると、心不全の進行が主な要因として考えられていますが、お薬の量が影響を与えた可能性もゼロではない、とのことでした。
と、医師の言葉をそのまま伝えることが大切です。
自分の推測を加えたり、『おそらく影響はないと思います』と断言するのは避けましょう。
あくまで医師の見解を冷静に伝えることで、相手も納得しやすくなります。
誠意をしっかり伝える
単に謝罪するだけではなく、相手にしっかり気持ちが伝わるようにすることが大事です。

私たちも非常に心を痛めております
といった気持ちを伝えつつ、

今後はこうしたことが二度と起こらないよう、改善策をしっかりと実行していきます
と、具体的に改善する姿勢を示すと、誠実さが伝わりやすくなります。
また、

お母様とご家族の皆様が少しでも安心できるよう、全力で対応させていただきます
という言葉を加えることで、さらに気持ちが伝わります。
まずは謝罪し、言い訳はしない

ご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありません
と、まずはしっかり謝罪することが大切です。
謝るときにすぐに『確認不足でしたが、事情があって…』と説明を始めると、言い訳をしているように受け取られることがあります。
まずは相手の気持ちに寄り添い、謝罪の意をきちんと伝えることが一番大事です。
再発防止策を具体的に伝える

今後は、お薬をお渡しする際に二重チェックを必ず行い、スタッフ同士での確認も強化します
といった、具体的な対策を伝えることが重要です。
『注意します』だけでは漠然としていて、相手に不安を与えてしまいます。
どう改善するのか、具体的に伝えることで、再発防止にしっかり取り組んでいることを伝えることができます。
最後に謝罪と締めくくりを柔らかく

このたびは、私たちの不手際でご心配をおかけし、本当に申し訳ありませんでした。
お母様が一日でも早く回復されることを心よりお祈りしています。
と謝罪を伝えます。
さらに、

もし今後、気になることがあれば、いつでも遠慮なくお知らせください
と加えることで、サポートの姿勢がしっかり伝わります。
まとめ
今回は、調剤過誤の初動対応シリーズの第3回として、『患者さん(またはご家族)への電話連絡』について解説しました。
調剤過誤が発生した際、患者さんやそのご家族にどのように連絡すべきか、具体的な伝え方や注意点を詳しくお伝えしました。
電話連絡を通じて、患者さんやご家族に安心感を与えることができる一方、対応を誤ると信頼を失う可能性もあります。
そのため、冷静で誠実な対応が求められます。
今回紹介したポイントを意識することで、患者さんやご家族との信頼関係を築き、今後の対応に役立てることができると思います。
調剤過誤は誰にでも起こり得るものですが、適切な初動対応をすることで、誠意を持って問題を解決し、より良い医療サービスを提供することができます。
次回は【STEP3】『患者宅訪問と謝罪』について、詳しく解説していきますので、引き続きご覧ください。
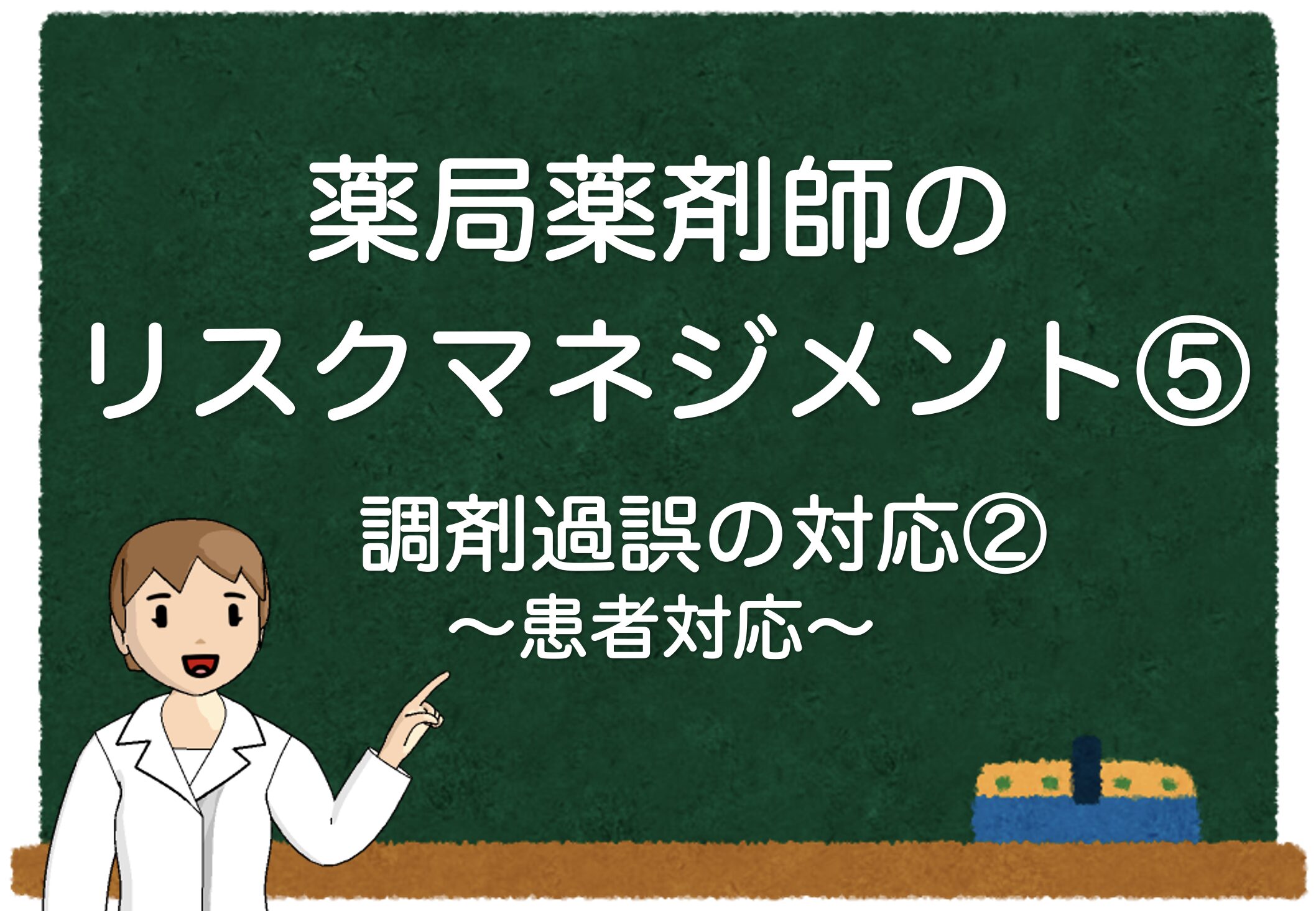
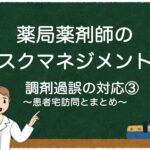
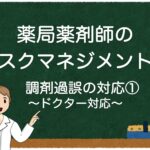
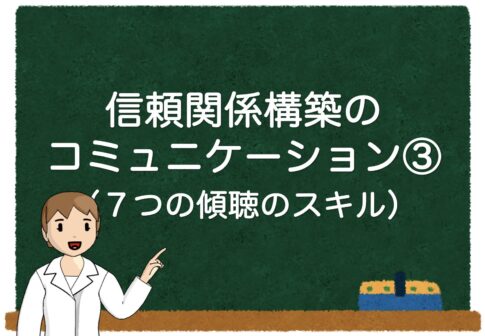
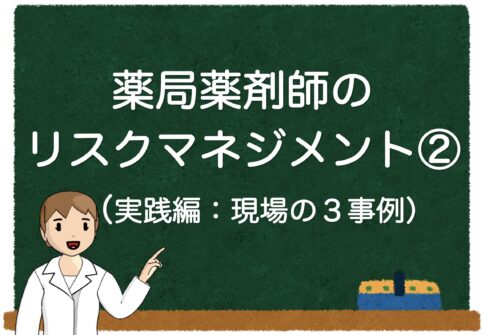
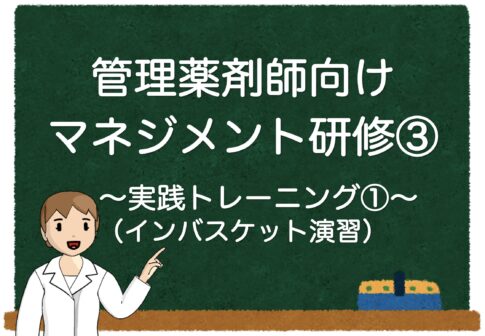
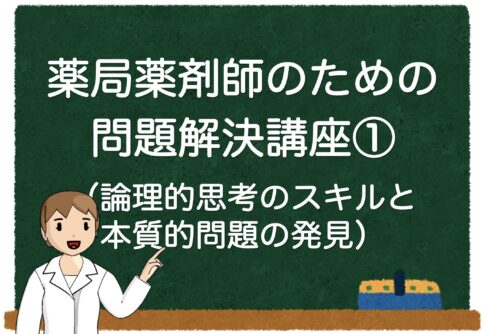
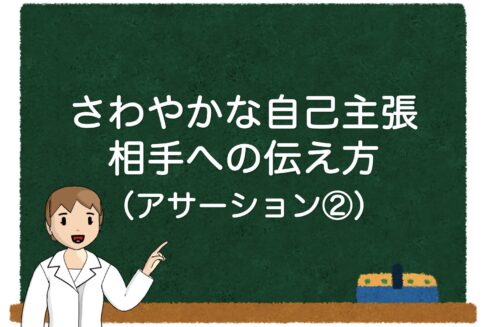
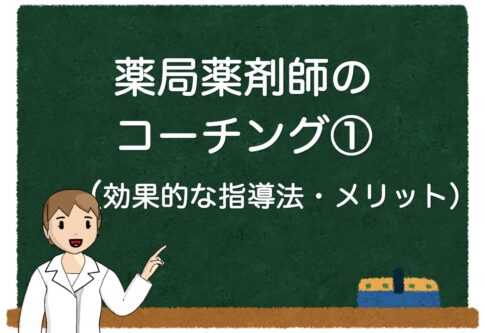
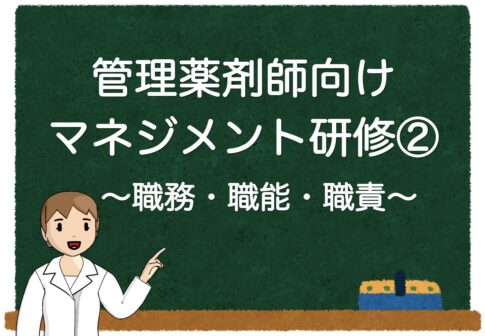
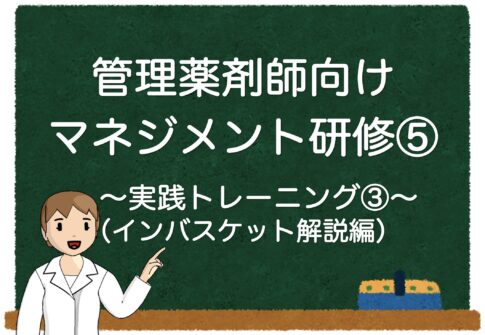

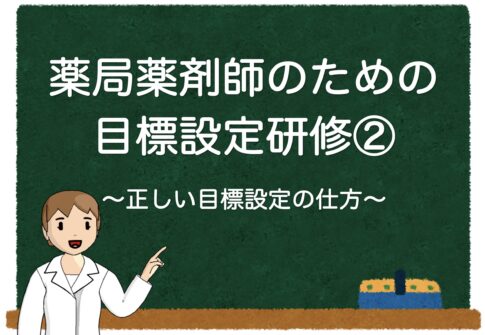

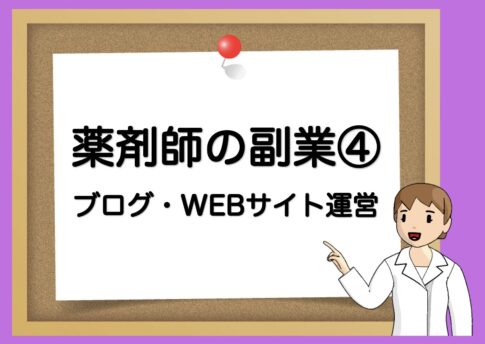
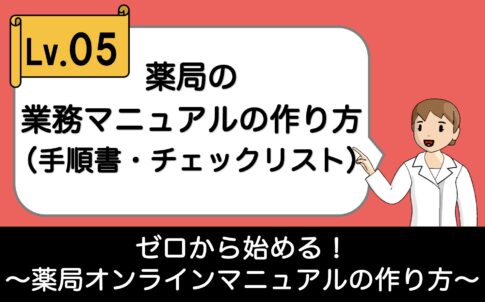
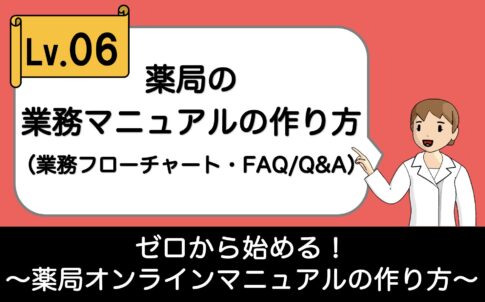

調剤過誤が発生してしまった…?