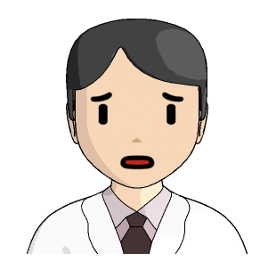
どうしよう、今すぐ報告すべき?
でも怒られるかも…
こんなふうに、調剤過誤でヒヤッとした経験ありませんか?
できることなら一生ミスなんてしたくない。
でも、薬局で働いている以上、どんなに気をつけていても、ミスをゼロにするのは難しいのが現実です。
『処方日数を間違えた』くらいなら、正直なんとかリカバリーできます。
でも、薬そのものを間違えたり、用量を誤ってしまったら…?
患者さんの体調に影響が出ることもあるし、最悪の場合、訴訟問題に発展する可能性だってあります。
薬剤師として、『ミスをゼロにするのが理想』なんてことは分かってるけど、現場で働いている以上、ヒューマンエラーを完全になくすのは正直難しいですよね。
だからこそ、ミスが起こったときにどう対応するかがすごく重要になってきます。
実際、調剤過誤の対応はクレーム対応と同じで、初動対応がすべてと言っても過言ではありません 。
最初の対応が適切なら、被害を最小限に抑えられるし、信頼を取り戻すことも可能です。
そこで今回は、調剤過誤が起こったときの初動対応 について、3回シリーズで解説していきます。
万が一のときに慌てないように、事前に流れを押さえておきましょう。
調剤過誤が起こった時の初動対応の手順
調剤過誤が起きたら、『まず上司に連絡!』これはどこの薬局でも基本ですよね。
でも、実際に現場で対応するのは管理薬剤師になることがほとんどではないでしょうか?
上司に報告はするものの、その場にいない上司は細かい状況がわかりません。
だから、実際に患者さんと向き合うのは、管理薬剤師や現場のスタッフになります。
これは『押しつけ』ではなく、最も適切に対応できる人が対応するというシンプルな理由からです。
逆に、状況をよく知らない人が患者さんに電話をすると、話がこじれることもあります。
私自身、過去の成功・失敗の経験から、調剤過誤発生時の初動対応は、以下の手順がベストだと考えています。
ドクターへの報告と確認
患者さん(またはご家族)への電話連絡
患者宅訪問と謝罪
実はつい先日も、大きな調剤過誤を2件対応しました。
どちらも訴訟になってもおかしくないケースでしたが、この手順で進めたことで、現場スタッフがしっかり対応できました。
この方法は再現性がある対応手順なので、あなたの薬局での万が一のときの参考にしてもらえればと思います。
今回はシリーズの 第1回目!
まず、上記の【Step1】の『ドクターへの報告と確認』について解説していきます。
真っ先にドクターに報告する5つの理由
調剤薬局で調剤過誤が発覚したとき、まずはドクター(処方医)に報告して、医師の判断を仰ぐことが大切です。
これには以下の5つの理由があります。
患者さんの健康を最優先に考えるため
調剤過誤が患者さんの体調に影響を与えている可能性がある場合、すぐに医師と連携して、必要な処置や治療を行うことが最優先です。
誤った薬や用量で健康に影響が出ている場合、対応が遅れることで症状が悪化するリスクもあります
なので、医師と迅速に連携を取ることが重要です。
誤投薬の医学的影響を確認するため
調剤過誤が発生しても、必ずしもすぐに健康被害が出るわけではありません。
ただし、医師の視点から誤投薬の影響を評価し、今後の対応を決める必要があります。
例えば、『どの程度影響が考えられるか』『追加の検査が必要か』『新たな処方が必要か』といった判断を医師に仰ぐことが必要です。
検査が必要な場合は、もちろんこちらで費用を負担します。
患者さんや家族への説明に医師の見解が必要なため
調剤過誤が起きた際、医師の見解を確認せずに謝罪すると、誤解を招くリスクがあります。
例えば、患者さんや家族から『薬の間違いで入院したんですか?』と聞かれた場合、薬局だけの判断で答えると、責任を過剰に負ったり、逆に説明が不十分だと感じられることもあります。
事前に医師の見解を聞いておき、『医師の判断では○○という見解でした』と伝えることで、患者さんや家族も納得しやすくなります。
医師の見解を記録に残すことで、後々のトラブルを防ぐため
調剤過誤に関する説明が後々訴訟や苦情に発展する可能性もあるため、医師の見解をきちんと記録に残しておくことが大事です。
例えば、医師が『薬の影響はない』と判断した場合、その判断をもとに説明できますし、『薬の影響が完全に否定できない』と判断された場合には、誤りを認めて謝罪を行うことができます。
このように、医師の見解をしっかりと記録しておくことが重要です。
医療機関との関係を良好に保つため
調剤薬局と医師の連携は患者さんの治療において非常に大切です。
医師に報告せずに薬局が独自に対応を進めると、後から医師が事実を知り、不信感を抱くことがあります。
それによって、医療機関からの協力が得られにくくなることもあります。
特に総合病院などでは、薬剤部を通じて医師と連携し、早期に情報共有することで、適切な判断が得られる場合もあります。
こうした5つの理由から、調剤過誤が発覚した際は、まず医師に報告して、しっかりと連携を取ることが大切です。
処方医に電話する前の7つのポイント
では、実際に処方医に電話する前に、以下の7つのポイントを確認して準備をしましょう。
医師の発言はできるだけ正確に記録する
医師が話したことはできるだけそのまま、引用できる形で記録しておきましょう。
後で確認したい時に役立ちます。
事実を正確に伝えつつ余計な言質は引き出さない
なるべく事実だけを伝え、薬局に不利になるような発言を引き出さないように気をつけましょう。
感情的な言い回しは避けるようにしましょう。
誘導的な質問はしない
『このミスが原因ですか?』みたいに、薬局側が100%悪い方向に話を誘導する質問は避けましょう。
できるだけ中立的に、事実を確認するように心がけてください。
見解は慎重に伝え、誠実な情報提供を心がける
嘘をついたり、隠したりしないことが大事ですが、不確かな情報を断定的に伝えるのもNGです。
あくまで事実に基づいた、誠実な伝え方を心がけましょう。
報告はできるだけ早くする
調剤過誤が発覚したら、すぐに連絡をしましょう。
影響を最小限に抑えるため、タイムラグを避けて、早めに報告をしましょう。
医師の指示をしっかりと確認して対応する
医師からの指示があれば、それをきちんと理解して、指示通りに対応することが重要です。
追加の処置や経過観察が必要なら、適切に対応しましょう。
やり取りはしっかり記録する
後で問題にならないように、電話でのやり取りや指示内容は必ず文書に残しておきましょう。
これで後々のトラブルを防ぐことができます。
この7つのポイントを意識して、ドクターに連絡しましょう。
それでは、実際の電話の流れを会話例でご紹介します。
医師との会話例
こちらは、薬局からドクター(処方医)への報告と確認の会話例です。
今回は、フロセミドの用量間違いを例に挙げて説明します。

先生、お忙しいところ申し訳ございません。
◯◯薬局の△△です。
□□さんの処方薬に調剤過誤があり、すぐにご報告したくお電話いたしました。
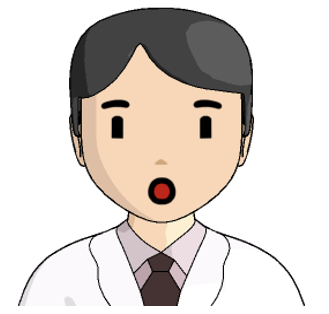
どういった内容ですか?

□□さんにお渡しするべきフロセミド80mgを、誤って40mgで調剤してしまいました。
患者様はそのまま服薬を続け、10日後に呼吸困難を訴えて入院されたと、入院先から連絡をいただきました。
現在、入院先の医師の診断について詳細は把握できておりませんが、まずは先生に事実をご報告し、ご見解を伺いたいと思いご連絡しました。
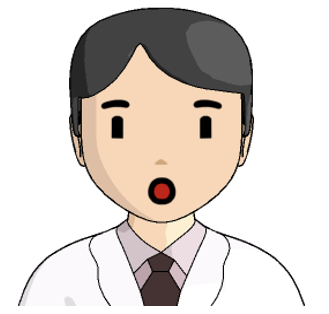
そうでしたか……。
フロセミドの減量が影響した可能性もありますね。
ただ、□□さんはもともと心不全が進行していたので、他の要因も考えられます。

確かに、以前から浮腫が出やすい状態とお聞きしていました。
今回の入院に関して、先生の診断では、今回のフロセミドの投与量がどの程度影響したと考えられますか?
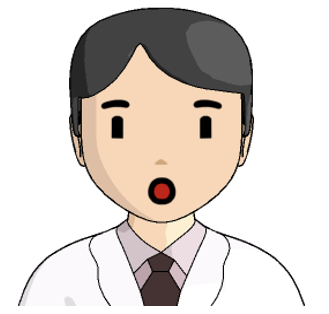
現時点では断定はできませんが、フロセミドの減量が症状の悪化要因の一つになった可能性はありますね。
ただし、心不全の進行自体が主因である可能性も十分に考えられます。

ありがとうございます。
それでは、患者様やご家族には、『医師の診断では、心不全の進行が主因と考えられるが、フロセミドの減量も要因の一つになった可能性もある』とお伝えすればよろしいでしょうか?
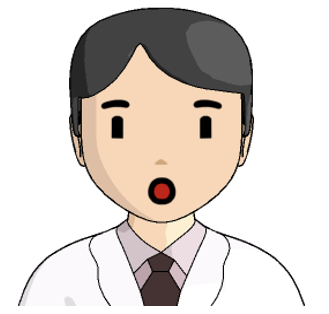
はい、それで問題ありません。

承知しました。
患者様やご家族に適切にお伝えし、今後の対応を進めてまいります。
また、今回の件について、先生から追加でご指示があればお願いいたします。
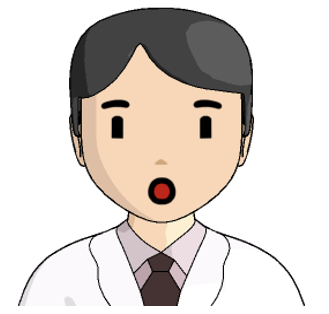
今のところ特にはないですが、入院中の経過を確認しておいてください。

分かりました。
経過を確認し、必要に応じてご連絡いたします。
お忙しい中ありがとうございました。
(通話終了)
処方医に電話する時の8つの注意点
先ほど会話例を紹介しましたが、実際に電話をかける場面では、ちょっとしたコツや気配りが大切です。
そこで、改めて電話対応時の注意点を8つにまとめました。
会話例とあわせて確認しながら、よりスムーズで的確な対応を意識していきましょう。
電話の基本マナーを守る
医師はとても忙しいので、電話をかける時間帯には気をつけましょう。
診療時間中は避けるのが理想ですが、急を要する場合は、診療の合間に連絡を取るようにします。
最初に自分の名前と用件を端的に伝える

先生、お忙しいところ申し訳ございません。〇〇薬局の△△です。□□さんの処方薬に調剤過誤があり、すぐにご報告したくお電話しました。
このように、まずは要件を簡潔に伝えることが大切です。
落ち着いて話す
調剤過誤を報告する場面では、焦ったり慌てたりしがちですが、冷静に話すことが大切です。
電話前に話す内容をメモしておき、落ち着いて話せるように準備しましょう。
事実を正確に報告する
医師に報告する際は、以下の3点を明確に伝えます。
- 何を間違えたのか(例:フロセミド80mgを40mgで調剤しました)
- 患者さんがどのくらい服薬したのか(例:10日間服用されました)
- 現在の患者さんの状況(例:入院先から、呼吸困難で入院したと連絡がありました)
このとき、主観的な表現は避け、『おそらく影響はないと思います』といった推測はしないことが重要です。
調剤ミスが入院の原因と断定しない
調剤ミスが直接の原因かどうかは、医師の診断によるため、『今回の入院は薬局のミスが原因です』と決めつけるような発言は避けます。
たとえば、
NG例:『調剤ミスのせいで入院された可能性があります』
OK例:『医師の診断では、心不全の進行が主因と考えられるが、フロセミドの減量も要因の一つになった可能性があるとのことです』
このように、事実を伝えつつ、医師の診断に基づいた説明ができるようにしておきます。
医師の見解を具体的に確認する
調剤過誤の影響について、医師の判断を明確にすることが重要です。
例えば、

『今回の入院に関して、フロセミドの減量がどの程度影響したと考えられますか?』
『今後の治療や対応について、薬局として注意すべき点があれば教えていただけますか?』
こうした質問をすることで、薬局側がどのように患者さんやご家族に説明すればよいか整理しやすくなります。
患者さんやご家族への説明内容を医師とすり合わせる
医師からの見解をもとに、患者さんやご家族への伝え方を確認します。

患者さんやご家族には、心不全の進行が主因と考えられますが、フロセミドの減量も要因の一つとして考えられますと伝えてもよろしいでしょうか?
といった具合に確認しておきます。
最後に医師からの追加指示を確認する
電話を終える前に、

今回の件について、何か追加の指示があればお願いします
と尋ね、医師からの指示を確認しておきましょう。
これにより、薬局として今後の対応が明確になります。
これらの注意点を守ることで、患者さんやご家族に適切に説明でき、医師との認識のズレも防げます。
結果として、薬局側のリスクを最小限に抑え、誠実な対応ができることになります。
緊張する場面ですが、冷静に、事実を正確に伝え、医師の意見をしっかり確認することが大切です。
まとめ
今回は、調剤過誤の初動対応シリーズの第1回として、『ドクターへの報告と確認』について解説しました。
調剤過誤はどんなに注意していても起こりうるものですが、その後の対応次第で患者さんへの影響や信頼回復の可能性は大きく変わります。
特に、医師への迅速かつ的確な報告は、患者さんの健康を守るうえで欠かせません。
報告時には、事実を正確に伝えるだけでなく、医師の見解をしっかり確認することが重要です。
これにより、患者さんやご家族への説明がスムーズになるだけでなく、医師の見解を記録に残しておくことで、後々のトラブル防止にもつながります。
次回は『患者さん(またはご家族)への電話連絡』について詳しく解説しますので、引き続きご覧ください。
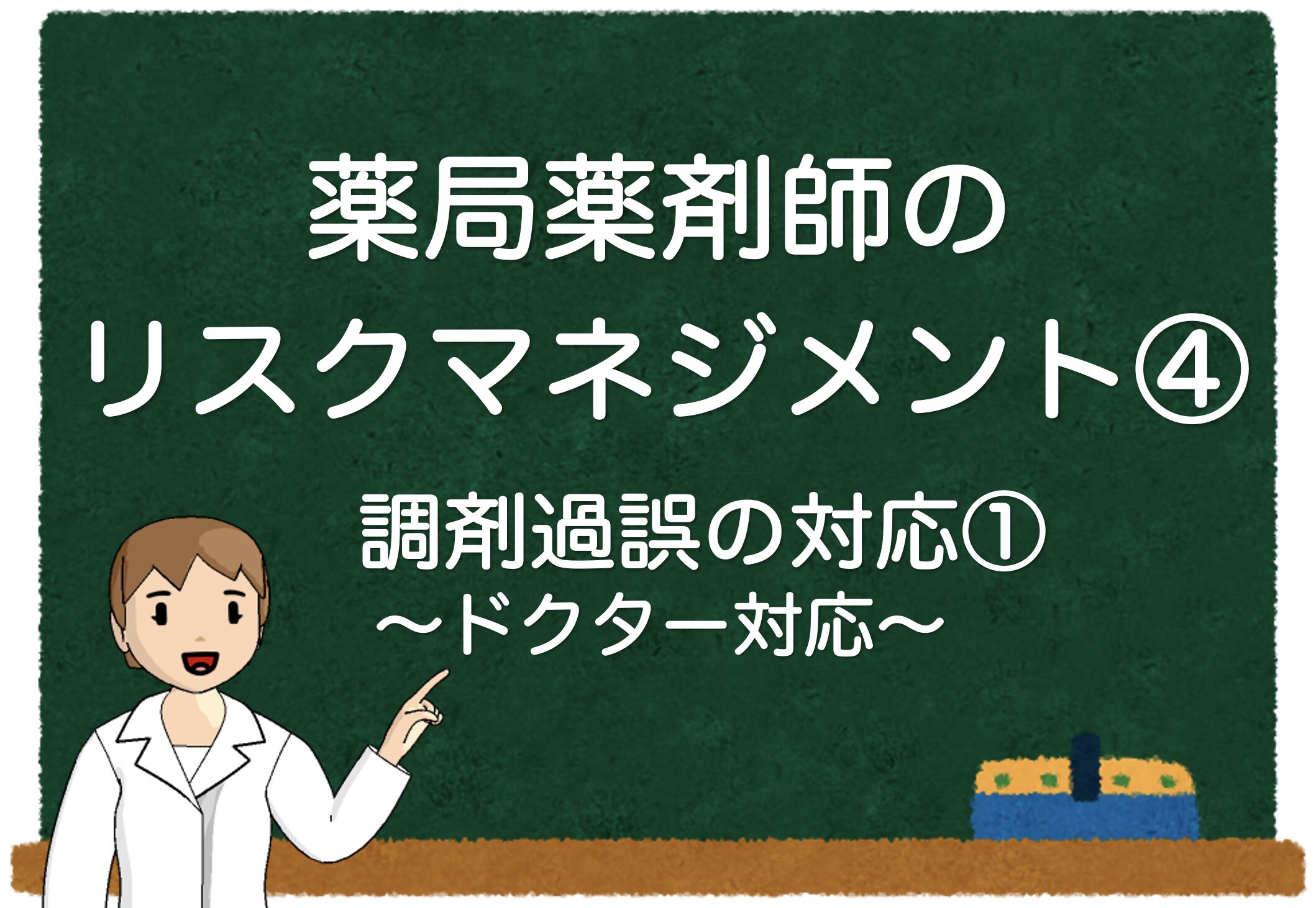
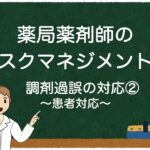
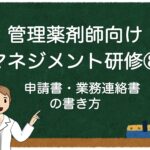
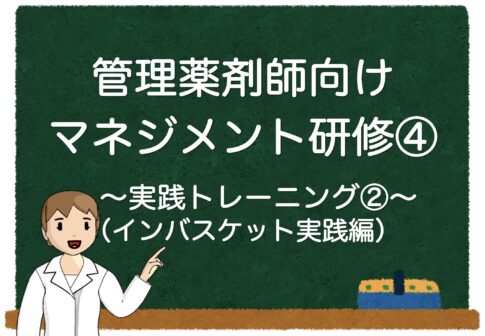
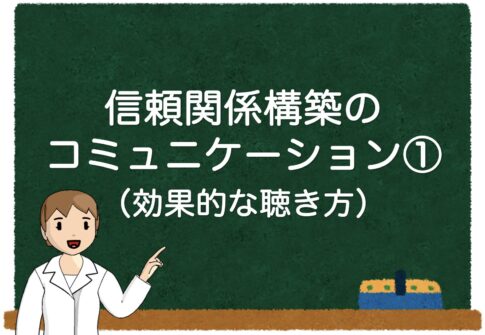
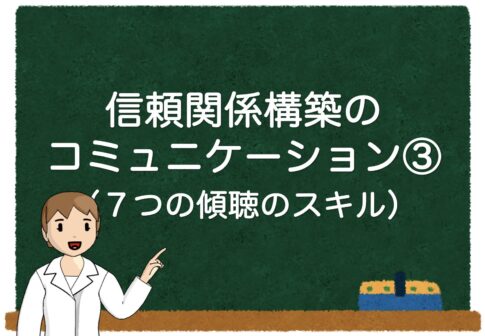
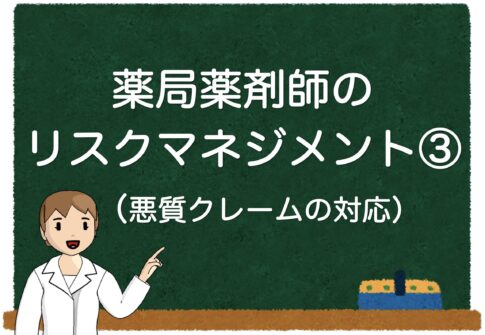
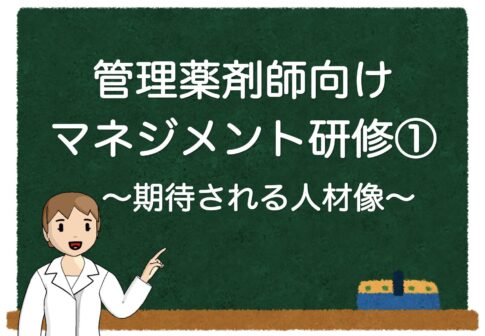
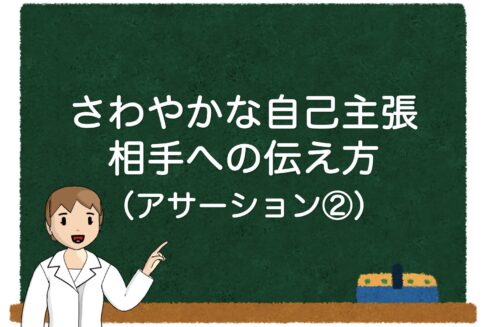
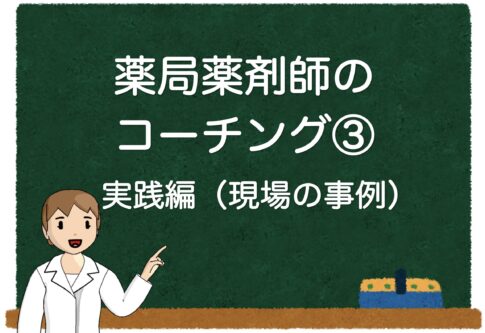
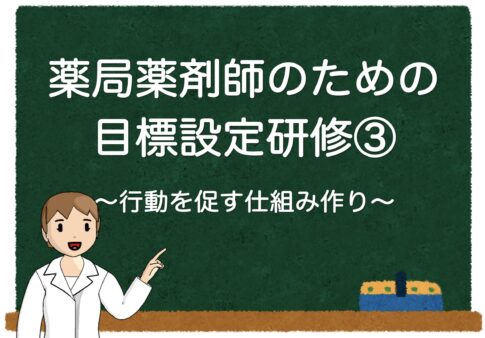

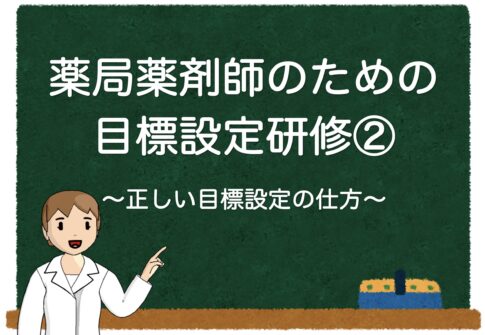

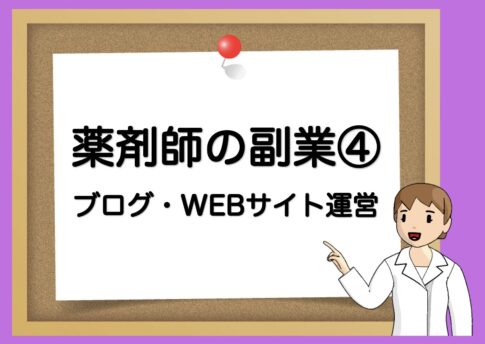
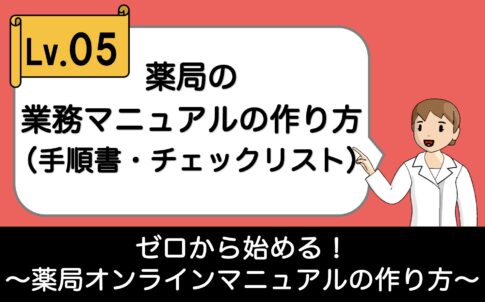
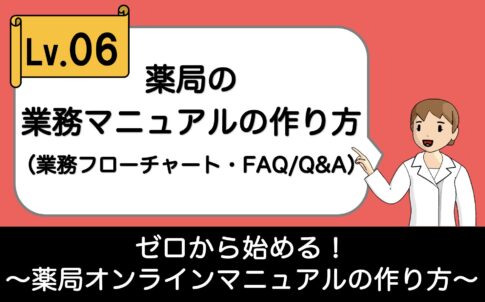

ヤバい…これ、調剤過誤かも…?